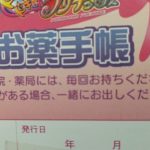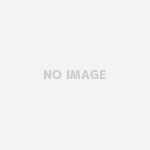田作り / Hirotaka Nakajima (nunnun)
関西のほうでよく使われる「ごまめの歯ぎしり」と言うことわざ。意味は何?と気になる人はいませんか。
ごまめって田作りだよね?煮つけがなぜ歯ぎしり?というところも不思議に思います。そこで、ごまめの歯ぎしりの意味と、なぜ田作りなのかについて検証しました。
ごまめの歯ぎしり(鱓の歯軋り)の意味
ごまめの歯ぎしりの意味・・能力のないものや実力にないものが、悔しがったりいきり立ったりすること
また
力のないものは、どんなに頑張ってもどうにもならない
という意味にも使われます。
なぜ「鱓(ごまめ)」なの?
ごまめとは・・①カタクチイワシの素干し ②またはそれを醤油や砂糖みりんで煮詰めたもの
素干しが歯ぎしりするということ?と疑問に思う人もいるのではないでしょうか。
古くは小魚の素干しのことを「こまむろ(細群)」と言っていたそうです。大量に群れをなす小魚のことを、そのように読んでいました。
この「こまむろ」が「ごまめ」に変わったという説があります。もともとごまめ自体も方言に分類されます。
また、昔、年齢の若い殿原(お侍さんの身分のひとつ)のことを『小殿原』=ごまめと呼んでいたことから来るという説もあります。どちらにせよ
ごまめ=小物や小魚が悔しかって歯ぎしりても無駄
という意味になったというわけです。
関西地方では、自分より小さい子供や、能力のない人をごまめという言い方をすることがあるそうです。あのこは「ごまめ」だから・・なんて言い方をすることがあります。
ごまめの歯ぎしり(鱓の歯軋り)に似たことわざ
ごまめの歯ぎしりに似たことわざはけっこうあります。昔の人は、たとえ上手です。そしてチャレンジャーな人も多かったのでしょうか。
以下、ごまめの歯ぎしりに似たことわざを集めてみました。
「石亀の地団駄(いしがめのじだんだ)」
亀が空を飛びたくて地団太を踏むさま
「雑魚の魚交じり(ざこのととまじり)」
小さい魚が大きな魚の中に交じっているさま
「蟷螂の斧(とうろうのおの)」、「隆車に向かう蟷螂 (こうしゃにむかうとうろう)」
蟷螂=カマキリが斧に似た前足をあげて、大きな車に立ち向かうさま
「泥鰌の地団太(どじょうのじだんだ)」
わずかな足びれしかないドジョウが地団太を踏んでも踏めないさま
「小男の腕立て ( こおとこのうでたて )」
力のない小男が腕力で戦おうとするさま
「小舟に荷が勝つ(こぶねににがかつ)」
小舟よりものせる荷物が大きすぎるさま
どのことわざも、情景が浮かべば、意味の想像がつきますね。いずれもごまめの歯ぎしりの意味とよく似ています。
豆知識 ごまめと田作りの違い
ココでちょっと豆知識です。お正月に登場するあの、小魚の煮つけのことをごまめと言ったり田作りといったしますよね。ごまめと田作りの違いって?と気になりませんか。
ごまめ=戦国時代に登場した表現で、俗っぽい言い方。いわゆる普通の呼び名で江戸時代の半ば以降に、正月料理のなかでも使われるようになった。
田作り=江戸時代の前半から言われるようになった言い方で。正月料理に関連付けた表現。
ごまめのほうが、古くから普通に使われている表現で、田作りはその後、お正月料理の一品として使われるようになり、さらにその後、同じ意味でつかわれるようになったということです。
終わりに
気になるごまめの歯ぎしりの意味でした。ごまめは昔、小さい魚あるいは経験の少ない若いお侍さんという意味があった・・。
それで小魚の歯ぎしりという意味につながったのでしょう。昔の人は、比喩やたとえが本当にうまいと感心します。